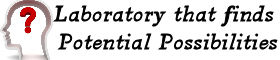時間と質
サッフォーの詩の影響で、時間をエネルギーという質的なもので捉えるようになったことは私にとって大きな変化といえる。もしかしたら、ずっと求めていたものが当たり前すぎるぐらい身近にあったことにも気づけるかもしれないと思った。今日はそのことを考えてみたい。
これも「書く」ことにつながることだ。3年ほど前だったと思う、私はコーチングのトレーニングプログラムを受講していて、毎回の相互練習のために自分がクライアント役の時に出すテーマを「とにかく論文を書きたい」というテーマで4か月過ごしたことがあった。その最終日のワークで「子供のころに過ごした夏休みの時のような感覚を持ちたい」というテーマにした。子供のころ、小学生の夏休み、何にもすることがなくてぼーっと過ごして時間は永遠にあるような気がしていたあの頃。トレーニング中の慣れないコーチたちにとっては、なんだかわけがわからない漠然とした全く頭の痛くなるテーマだったと思うが、私にとっては非常に現実感があるテーマだ。私の中にある感覚を探求するのだから、ないものを考えるわけではないからだ。そのセッションでは、探求自体は進まなかったが、私の中でその必要性は強まった。
なんとなく自分の中に欲している漠然とした感覚を言語化するのは重要なことだ。気づきはそこからしか出ないだろうからである。では、なぜその感覚が欲しくなったかといえば、そのころ書きたいと思っていたことを行動に移すには、そのぐらいの永遠と思える時間と、どうでもいいことを許すゆとりと、とどまっていられる静けさが必要だったからだろう。それほど、私にとって書くということは、気が遠くなるような、骨の折れるとても難しい時間がかかる作業というイメージがずっとあった。もちろん頭ではそうではないことは半分わかっているのだが、なんとなく持ってしまっているイメージというものの力は、実は計り知れないほど大きいのだ。人は、その力の前であっさりと負けを認め相手に道を譲ってしまう。そして日常の煩雑な声の方を聞くようになってしまう。それは、そこに入らないための騒がしい声。感覚もじっとしていることができないような、次のことやほかのことが気になるモンキーマインドの状態の声だ。そして心の奥から聞こえてくる本当の声はあまりにも小さくて不明瞭なので、気づかないか、それをわかろうとする作業を面倒に思って先延ばししてしまう。そして、またいつか、いつでも書こうと思えば書ける、今書かなくても。という声の方を聞いてしまう。でも、それは永遠に自分をだまし続けるだけの声だ。
その時のテーマ「子供の時の夏休みを過ごした時に持っていた感覚」要するに時間の感覚のことだが。小学生のころ、それも3年生ぐらいのころのことだが、そのころの夏休の記憶というと、その日何をすることも決まってなくて、遊ぶ友達も誘いに行ってもいないので、一人で遊ぶしかなかった時が思い出される。今その感覚を欲しているから特にそのことばかりを思い出すのかもしれない。その思い出の中にある時間の感覚は、まるで時間は永遠に続くような感覚で思い出せるのだ。私は空想好きな子供だったので、一人の時はたいていいろんなことをただただぼーっと考えていた。といっても内向的ではなかった。普段は近所の友達を片っ端から誘いに行っては公園で遊ぶのが最優先事項だったので、このような時間はそんなにあったはずはないのだが、今思い出すと、このぼーっと過ごしていた記憶だけがよみがえってくる。
どうしてあのような感覚を持っていたのだろうか?はなはだ不思議である。なぜなら、私はいつも遊んでいるとすぐに暗くなって家に帰る時間になってしまうという感覚もあり、その時間がとても嫌いだったからだ。ずっと昼間だったらいいのにと思っていた。永遠の時間を感じていた自覚はないのに、今思い出すとその感覚があったように感じるのはなぜなのか。単なるないものねだりなのか。
でも、それも時間を質的な視点で見ることで、小さい頃の他の感覚でも捉えなおせるような気がしてきた。それは幼稚園から小学校低学年のころの記憶に遡る。私の父は福井県敦賀市で家具やを営んでいた。正式には、父の兄が経営していたのかもしれないが、取り仕切っていたのはほとんど私の父だったと記憶している。敦賀でもかなり大きな家具店だったので、店の中はかなり広く3階まで各階ぎっしりと商品が並んでいた。祖父母はその3階部分に住居用の場所を設けてもらい、そこに住んでいたので、私は幼稚園からその店に帰らせてもらい、祖母におやつや、ごはんも食べさせてもらっていた。その店では何人も従業員を雇っていたが、その中には私の母も交じって店員として手伝っていたので、夕方母が帰る時までその店が私の遊び場になっていた。私はその店で一人で遊ぶのが大好きだった、たまに従妹たちが来ることがあったが、すきを見てはひとりでこっそり店の中を探索した。
その探索というのは次のようなものである。まず初めは三階部分から。そこには高級品が置いてあり、私はたくさんん並んでいるその高級タンスの扉や引き出しの表面に施してある彫り物を慎重に掌と指でなぞりなぞったり、開け閉めする。目ではその材質の表面の色と質感を感じ、手でその手触り、鼻では材料になっている木材独特の匂いや塗料の匂い。耳では扉の開け閉めの時の精密なカチャッという音を楽しんでいた。さらに、扉を開けた時のあのひんやりとした空気が出てくるのも好きだった。次は二階に降りる。そこには一面にベッドが置いてあり、靴をぬいで、一通り全部のベッドの上を走って移動する。一面のトランポリンのような場所だ。ただ、これは本当はしてはいけないことだったので、一回だけで我慢。さらに、応接用の家具、ソファーや飾り棚、サイドボード、輸入家具など。それも一通り座ったり開け閉めしたり触ったりする。そして一階に降りると、そこには日常的な家具全般が置いてあった。一般的な食器棚やカラーボックス、食卓テーブル、ベビーダンスや安い整理ダンスやロッカー類が所せましと置いてある。私はそこも一応すべて開け閉めしてじっくりと吟味し、うんざりした気分になる。私はその人工的な、いわゆるハリモンと呼ばれる家具が大嫌いだった。それは合板に光沢のあるどぎつい色の板を貼ってあるものが多く、中に使ってある木材も3階のものとは雲泥の差だ。さらに、テーブルなどに使われているそのころはやっていたメラミンはその名前とともになんともいやな気分がした。私はそのものたちをほとんど憎んでいたほどだったので、どうしてこんなに醜いものを作るのかが全く分からなかった。(ちなみに自分の家に置いてある家具はすべてこのランクの家具だった)一通りその憎しみを感じた後、再び3階にあがり大好きな高級家具に浸る。これを繰り返すのが私の大好きな一人遊びであった。
店の人たちは私が何時間でも行ったり来たりするのをみて、いったい何がおもしろいのかわからなかっただろう。とはいえ、私も私なりにわきまえていたので、お客さんが一人でもいたら、おとなしくおばあちゃんのいる部屋に引っ込んでいたし、ベッドの上を走っているところを見つかったこともないので、邪魔になることはなかっただろう。それどころか、タンスを布で拭いて回るお手伝いも買って出ていたぐらいだ。子供の私にまとわりつかれることもなかったはず。自慢にもならないが。店は私にとって大切なものが置いてある神聖な場所ですらあった。
本題に戻れば、なぜこのころのことを書いたかといえば、このころの私は全身の感覚を使って、その物質たちの質感からそのものたちの価値を測っていたということを言いたかったのである。
それは、違う言葉を使えば、本物か偽物かということであり、天然か人工か、丁寧か粗雑か、吟味されているか顧みられていないか、大事にされるの使い捨てにされるのか、そのことを全般に踏まえたうえでの快、不快につながってくる。私の物事の測る基準はきっとこのころに培われたのだ。
要するに、子供のころはすべてを質で測っていたのである。今もその感覚を使っているとはいえ、一般に数字、即ち量的に測るものは質では見なくなっている。子供のころは数字で測るものでさえ質的、即ち感覚で測っていたのだ。
子供のころ、遊びに夢中になているとすぐに暗くなってしまうというのもそうだ。母から門限も時間で言われていたが、帰るのを決めるのは外の暗さだったり、定時に市役所が鳴らすサイレンだったり、友達が一人帰り、二人帰りして、最後には遊ぶ友達がいなくなっていく感覚だったり。それも友達の人数で決めるというよりは、存在としてのそれだっただろう。やがて、大人になるにつれて知らず知らずのうちに私は時間を量的なもので測るようになり、やがてそれが定着する。そして、小さい頃のそれと比べようもないくらいその変化に気づいていない。時間を何かに換算するようになるとそれが始まったのかもしれない。中学に入って、たくさんの宿題や、試験勉強の時間を一つの教科に何時間かけるか、とか、速度の計算も苦手だったが、やがてそれも違和感を感じなくなる。そして、さらに、アルバイトで時給というものに換算するようになる。やがて、時間はその質感を失い、有限なものとして出現し始める。
この量的なものと質的なものの視点は、岸見一郎先生からのものが最初だ。岸見先生はその著書や講演で、三木清の言葉を紹介しながら、幸福は質的なものである。だが、人の価値は生産性で測られていると。最初は頭でわかったつもりになっていたこの言葉だが、岸見先生の具体的な事例を聞くと、いかに私たちがその価値観に縛られていて、自然にそれで考えてしまっているかがわかる。本当に根本的なところから、本当は量で測ることができない感情や人生の質の幸福まで、成功というわかりやすい量的な物差しを採用しているのだ。
岸見先生はこうも話されていた。時間も量で測れば有限になり、質で見ればその一瞬一舜が永遠になると。まさに、子供のころの質ですべてをはかっていた感覚がこのことから説明される。
時間を計る。それ自体は生きていくうえで必要なことだということはっわかる。だが、時間というものを計っている側面だけで理解してしまっていないだろうか。最初人間は、単に仕方なく都合上量計るようになった。そのことは画期的な進歩だったかもしれない。だが、時間は本来そのような性質のものではないのだという認識が必要なのだろう。時間を計るということができると思っている人間の認識がそもそものズレなのかもしれない。
時間を時計で計るようになって、それが時間のすべてと思っている今は、人間の体重だけ計って、それが人間のすべてだと思っていることと同じだろう。
私は、いまや、あの時のテーマの答えを手にした。すなわち、あの頃の感覚を取り戻すには、時間を質的にとらえることが必要だということ。そして、それは、はるか昔のギリシャのレスボスの夕星をうたったあの視点から取り戻すことができそうだ。まずは、エネルギーの質的なものとして。
2020.6.9 am 12:20